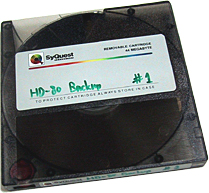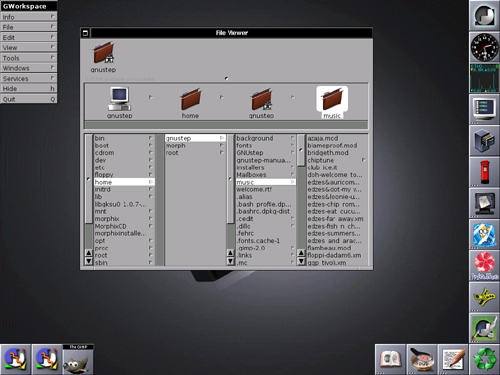29
元NASAの研究者が作ったというRobosapienが届きました。

2足歩行ができるおもちゃロボットです。操作は赤外線リモコンで行い、ボタンで67種類の動作が直接指定できます。複数の動作を組み合わせたマクロでの連続動作、手足に付いている接触センサー(スイッチですが)/腹部の音センサーをトリガーした動作の開始も可能です。
電源は、両足に2本ずつ入れる単1電池。早速動かそうと、コンビニに行ったところ、単1電池は置いてありませんでした。そういえば、単1なんていう大きな電池はしばらく使っていませんね。コンビニにないのも当然か・・・。
単5電池も置いていない店舗が多いようです。HPの電卓の電池がなくなったときに困ったことがあります。
単1電池が入手できたら、またレポートします 🙂